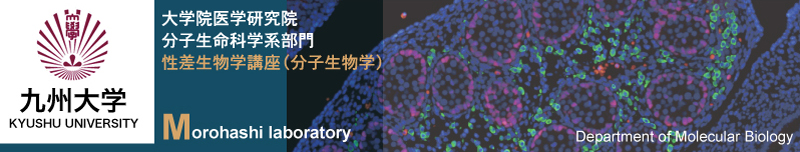教授のうわごと


性と多様性
自然科学研究機構 基礎生物学研究所 性差生物学研究部門
諸橋憲一郎
はじめに
雄と雌の2つの性が確立したことで、有性生殖による繁殖が可能となりました。当然ながら生殖の目的は効率良く自身の子孫を残すことですので、そこには個体間の競争や雌雄間の巧妙な駆け引き、すなわち生殖戦略が発達することとなったのです。2つの性の生物学的意義を単に精子と卵子の供給源として捉えるのであれば、生物の進化や多様性を説明するのは無理なのですが、遺伝的多様性の源泉として捉えることで、性の本質が見えてくるのだと思います。すなわち、この多様性こそが性を語る上で重要なキーワードなのです。
有性生殖を行う生物には雄と雌が存在します。この両者の役割は受精可能な生殖細胞、すなわち雄では精子、雌では卵子を作り出すこと、そして生殖活動を行うことです。その結果、個体は次世代へと遺伝情報を受け渡すことが可能となり、ひいては種の存続が可能になったと考えられます。この過程で非常に重要だったことは、生殖細胞が減数分裂を行う際に、相同染色体の間で遺伝的組み替えを行うことでした。父親由来の染色体と母親由来の染色体の間での組み替えは、新たな染色体の形成を可能とし、遺伝的多様性を作り出す原動力となったと考えられています。もちろん、精子と卵子の融合も遺伝的多様性を生み出したことは言うまでもありません。単為生殖では突然変異以外には遺伝的多様性の獲得は不可能であったことを考えれば、集団内における遺伝的多様性の獲得と維持に関する限り、有性生殖は単為生殖に対し圧倒的に優位であったと説明されてきました。そして、地球上に繁栄する実に多様な生物種を生み出したのは、有性生殖を介した遺伝的多様性の獲得の結果であると理解されているわけです。
1.生殖と多様性
(1)種の多様性と生殖
種が分化するためには生殖の隔離が必要です。たとえば、ある動物がある地域に生息していたとします。その地域に地殻変動が生じ、生息地域を分断するような大きな川ができてしまった。そうすると、川を隔てて2つの物理的に隔離された地域が成立することになります。その結果、川の向こうとこちら側の動物の間では生殖を行う機会を失ってしまうわけです。このような理由で生殖が隔離されると、2つの集団は異なる遺伝的変異を蓄積してゆくことで、最終的には種が分化する、すなわち両者の間では子孫を残すことが不可能となるというものです。これはさもありそうな例です。もう1つの可能性は、1つの遺伝的変異が種の隔離を引き起こすというものです。生殖を成立させるためには数多くの遺伝子が関与することを考えると、どのようにしてたった1つの遺伝子変異が生殖の隔離を行うことができるのかという疑問が生じます。もちろん、複数の遺伝子に同時に都合の良い変異が入ることもあるかもしれませんが、そんなことはきわめて低い確立なので考慮する必要はありません。だから、たった1つの遺伝子がいかにして……という疑問が出てくるわけです。ところが、最近になってその具体的な例が見つかったのです。カタツムリには貝の巻き方が左右逆になったものが出現しており、この両者は交尾器の方向が逆になっているので、両者の間ではもはや生殖を行うことが不可能になっています。すなわち、生殖の隔離が起きてしまったわけです。そして、興味深いことには、すでにこれらの両者は異なる遺伝的変異の蓄積を始めており、いずれ異なる種に分化する運命にあるようです。このように、地球上に繁栄する多様な生物種を確立するにあたって、生殖は力強い原動力となってきたということです。
(2)繁殖戦略の多様性
多様な生物種の確立過程で生殖の果たした役割は非常に重要なものでしたが、これらは生殖がもつ本質的な特徴、すなわち多面的な多様性と密接に関わるものだと考えられます。その1つが繁殖戦略における多様性です。種の継続と繁栄には、個体がいかにして多くの子孫を残すかという繁殖戦略こそが重要であったと言われています。そのために雄同士が個体間で熾烈な競争を繰り広げることがあります。たとえば、精子競争はその代表的な例として議論されてきました。雌が複数の雄個体と交尾する動物では、雄は他の雄の精子と競争しなければなりません。もっとも簡単な競争は精子数を増やすことで、自らの精子が受精にあずかる確立を高くすることですが、それ以外にも自分より前に交尾した雄の精子を殺してしまうやり方や、交尾の後に腟の開口部に栓をしてしまうことで、他の雄の交尾を不可能にするやり方もあります。いずれにしても、この競争を勝ち抜くために、雄は多様な戦略を駆使してきたのでした。このような競争は種の継続や繁栄というよりは、むしろ自身の子孫をいかに多く残すかという競争であり、その結果として種の継続や繁栄がもたらされたと理解すべきことだと思います。このように雄個体間での競争が繁殖戦略の多様性の獲得に寄与した側面があると同時に、雌同士の競争や、雄と雌の間での競争も存在することが予測されます。実際にそのような個体間競争もあって、きわめて多様な繁殖戦略を駆使しながら、いかに効率良く子孫を残すかという工夫がなされてきたのです。
(3)自然淘汰と性淘汰
工夫するといっても、個体の努力で何とかなることでもありません。遺伝的変異が形質の変異を引き出し、さらにその変異が選択され、最終的に集団内に定着することが必要なのです。そこにはどのような選択過程があったのでしょうか?遺伝子の変異がある確立で集団内に出現し、多様性の獲得のための原動力となったことは、すでに述べた通りです。この変異によってもたらされた表現型が集団内に定着しなければ、いずれは消失してしまいます。しかしながら、それが個体の生存に有利に働く場合には、この新たな形質が集団内に定着することになります。一般には、そのような形質の選択は自然淘汰によって行われるわけです。その場合、生存に不利な変異は淘汰されるのが原則です。ところが、どう見ても生存には不利だろうと思われるような形質が残されることがあります。たとえば、婚姻色や尾長鶏の尾はその典型です。目立つ色は捕食者に見つかりやすいだろうし、長い尾は捕食者から逃げる時には邪魔なはずです。ところが、そのような形質が保存されている。これは自然淘汰では説明できません。それでは何がそのような選択をさせているのかということです。たとえば、婚姻色を呈する個体の方が効率良く異性を引き寄せることができたり、長い尾をもつ雄の方が雌に好まれるのであれば、これらの形質はある頻度で次世代に受け継がれることになります。逆に、自然界で生き抜くのに有利な形質であっても、配偶相手に対して何の魅力にもならない、むしろ嫌われるようなものであれば、その形質は集団中から消失してゆくはずです。このように、自然淘汰では説明できない形質の選択が生殖を通じて行われることがあり、性淘汰と呼ばれています。そしてこの性淘汰こそが繁殖戦略における多様性の確立に重要な役割を果たしてきたと考えられているのです。
2.性決定の多様性
さて、これまで述べてきた多様性は、種分化の過程や生殖戦略に生殖が深く関わることで獲得されたものです。生殖に関わる事例で、もう1つ多様性を示す興味深い事例があります。それが性決定の多様性です。雌雄がその目的を達成するためには雌雄で異なる生殖腺(精巣と卵巣)を分化させること、すなわち性を決めることが必要です。そして、この性決定に求められる重要な点は、集団中に2つの性の存在が保障されなければならないことです。どちらかの性のみが分化してしまうようなことが起きれば、その種は絶えてしまいます。したがって、2つの性の存在が保証されることが重要なのですが、それさえ満足できれば性決定の様式はどんなものでもよいはずです。そして、実際に広く動物界を眺めれば、性決定の様式がいかに多様な分化を遂げたかを知ることができます。
(1)遺伝子か環境か
一般には、性は遺伝子によって決まると理解されています。ただ、先ほども述べたように、性決定に求められる最低限の条件は雌雄の存在が保証されることですので、それさえ満足できればどんな方法でも構わないわけです。そしてご存知かもしれませんが、実際には遺伝子以外の要因が性を決めている生物も多いのです。有名な例ですが、ある種の魚では成熟した精巣や卵巣が、年齢や社会的地位によって、逆の性に転換することがあります。このような生物を見る限り、性は固定されたものではなく、変わり得るものであり、遺伝子が性を決定しているのではないと言えます。そのような動物であっても、雌雄の存在が保証され、種が絶えることはなかったのです。また、これも有名な例なのですが、ウミガメやワニは卵が置かれた温度によって性が決まります。したがって、これらの生物においても遺伝子が性を決めているわけではないのです。ただし、これらの動物種では、いったん性が決まると、その後に性が変わることはありませんので、性転換する動物とは性決定機構は異なると考えられます。このように外的要因によって性が決まる動物以外に、性染色体をもつ動物がおり、これらの動物では遺伝子が性を決めているわけです。つまり、遺伝子が性を決める動物と、遺伝子以外の要因で性が決まる動物が存在するということです。性決定における多様性の1つの例です。
(2)性染色体の選択
遺伝子が性を決める動物の場合、雌雄で異なるセットの染色体があり、これを性染色体と呼んでいます。これに対し通常の染色体は常染色体と呼ばれます。2本の常染色体は同じセットの遺伝子から構成されていますが、性染色体の遺伝子構成は異なっています。哺乳類のようにX染色体とY染色体の大きさが明らかに異なる場合には、そこに存在する遺伝子構成に差があるのは明白ですが、大きさがほとんど変わらない場合でも、少なくとも性決定遺伝子の有無については差があることになります。性決定遺伝子については後で述べることにして、まず性染色体の選択について述べたいと思います。性染色体は、もとは常染色体であったと言われています。つまり、すべての染色体は常染色体だったということです。このうち、ある常染色体が性染色体として選ばれることになるのですが、この選択に不可欠なのが性決定遺伝子の獲得だったと考えられます。すなわち、性決定遺伝子としての機能を獲得した遺伝子が偶然に乗った染色体が性染色体となった、あるいはある染色体に乗った遺伝子が性決定遺伝子として選択されることで、その染色体が性染色体としての座を獲得したということになるのでしょう。もしそうであるならば、後で述べますが性決定遺伝子の選択は偶然の産物ですので、性染色体の起源は動物種によって異なってよいはずです。この点については、実際に異なっているという結果が染色体マッピングの実験から得られています。そうすると、性染色体の選択において重要なことは性決定遺伝子の獲得の機構になります。いかにして性決定遺伝子が作られたかということです。
(3)性決定遺伝子の多様性
これまでに哺乳類とメダカで性(精巣)決定遺伝子が同定されています。これらの動物はXYの性決定様式をとり、異型の性染色体を1本ずつもつ個体が雄に、2本のX染色体をもつ個体が雌に分化します。XY以外にZWの性決定様式を採用した動物もいます。鳥はその代表例で、異型の染色体を1本ずつもつ個体は卵巣を、2本のZ染色体をもつ個体は精巣を分化させます。したがって、XY型とZW型では性決定遺伝子の機能は異なります。すなわち、Y染色体上には精巣分化を決定する遺伝子が、W染色体上には卵巣分化を決定する遺伝子が乗っていることが推測されてきたのです。実際に、哺乳類で同定された性決定遺伝子(精巣決定遺伝子)であるSRYとメダカの性決定遺伝子DMYは予想通りにY染色体に乗っていました。これらの遺伝子の塩基配列からは、SRYとDMYは転写因子様の構造を有していることが分かりました。しかしながら、SRYはHMG box、DMYはDMdomainと呼ばれる、異なるタイプのDNA結合ドメインをもっていたことから、これらの遺伝子が異なる祖先型遺伝子より派生したものであることが確実となったのでした。すなわち、進化の過程でこれらの動物は異なる遺伝子を性決定遺伝子として選択したということです。しかも、メダカといっても、いろいろな種のメダカがいるなかで、すべてのメダカがDMYを性決定遺伝子として採用したわけではないという興味深い結果が得られています。すなわち、進化的にはメダカの分岐以降に、ある種のメダカでDMYが性決定遺伝子としての地位を獲得したということであり、メダカの祖先型はDMY遺伝子を使わない性決定を行っていたということを示唆するわけです。鳥類や哺乳類の性決定機構についても同様の推論が可能で、鳥類の分岐前後に卵巣決定遺伝子を獲得したであろうし、哺乳類の分岐前後に精巣決定遺伝子SRYを獲得したのだろうと考えられます。なぜそのような特殊な時期に性決定遺伝子が出現したかは後で述べます。ともかく、性決定遺伝子の多様性は進化上必然であったということなのです。
生物の機能や組織形成にとって重要な遺伝子は動物種を越えて保存されているのが一般的ですが、この考え方では多様な性決定遺伝子の選択を理解することができません。まるで、行き当たりばったりの選択が行われたように見えます。偶然の選択というのでしょうか。ただ、これは半分が進化の必然で、残りの半分は生殖の特殊性を繁栄していると考えられます。つまり、遺伝的変異はもともと行き当たりばったりです。通常はこのような行き当たりばったりの変異は自然淘汰や性淘汰によって選択されるので、生存や生殖に有利な形質が残ることになります。性決定の場合はどうかというと、性決定遺伝子が登場する前から種が存在していたのだから、そこには雄と雌はいたわけです。つまり、性決定遺伝子というか、遺伝的性決定は必ずしも必要ではなかった。そのような状況で性決定能を有する遺伝子が登場したのだと考えられます。だとすれば、性決定遺伝子が残るためには,遺伝的性決定がそれ以前の性決定より優れていなければなりません。素人の推論ですので、話半分に聞いていただきたいのですが、遺伝的性決定が優れている点は、常に雌雄が半分ずつ生まれるということです。環境などの要因に左右されることなく、雌雄の存在が保証されるということです。温度依存的性決定を行うウミガメなどは産卵する浜の温度が変化してしまったら、生まれる仔の性比が偏ってしまい、いずれ絶滅してしまいます。遺伝的性決定を採用することで、そのような危険にさらされることがなくなりました。もう1つの推論は、やはり温度と関係があります。これまでに遺伝的性決定を採用した動物種、つまり哺乳類と鳥類は自然環境に左右されることなく、卵の温度と胎仔の温度は親の温度に依存します。鳥は卵を温めますし、哺乳類の胎仔は母体の中で育ちます。したがって、進化的には鳥類より古い爬虫類が採用した温度依存的性決定は、これらの動物では採用できなかったわけです。温度依存的性決定から遺伝的性決定に進化することが、これらの動物の出現には不可欠であったと理解すべきだと思います。すなわち、これらの動物の分岐前に性決定遺伝子が登場した。だから、鳥類はすべてZW型の性決定を行うし、哺乳類は共通にSRYを性決定遺伝子としたのだと理解できます。メダカの性決定遺伝子の獲得過程とは様子が違っているはずです。話しが少々ずれてしまいましたが、遺伝的性決定機構も多様であることが、進化の過程では必然であったということです。
(4)性決定遺伝子の必要条件
すでに述べたように、雌雄の存在を確保することのみが、性決定遺伝子に課せられた条件です。精巣と卵巣の形成に必要な遺伝子はすでにもっていたのですから、どちらの経路を選択させるかが性決定遺伝子の唯一の任務ということができます。その任務を遂行すれば良いので、同一の遺伝子である必要はなかったのでしょう。しかしながら、このことが性決定遺伝子の多様性を積極的に説明するものでもありません。同一の遺伝子を祖先型としても良かったのですから。ただし、すでに述べたように、多様な性決定遺伝子の獲得は進化の過程で行われた性決定機構の選択や、進化の過程における外界の温度依存性からの脱却と密接に関連があるはずですので、そのような種々の制限があるなかで、多様な性決定遺伝子が成立したと考えられます。
性決定遺伝子の多様性を理解するには、性決定遺伝子としての必要条件を考える必要があります。そしてそのためには、生殖腺の性分化のプロセスを理解しなければなりません。生殖腺形成のもっとも初めに、将来生殖腺に分化する細胞の集団、すなわち生殖腺原基が作られます。この細胞は性的に未分化な状態で、未分化生殖腺と呼ばれます。興味深いことは、この性的に未分化な生殖腺原基は、この段階で精巣にも卵巣にも分化する潜在的な能力を有しているということです。この未分化生殖腺の性を決める遺伝子が性決定遺伝子であり、このステップが性決定なのです。この性決定を経て、性的に未分化な生殖腺原基が精巣または卵巣への分化のステップを進むことになりますが、さまざまな遺伝子がこの過程に関与し、ある種の遺伝的プログラムを構成しています。プログラムを構成する上流の遺伝子がONまたはOFFを選択すると、下流の遺伝子にその選択が伝わり、ONまたはOFFを選択するという仕組みです。通常はこのようにして上流から下流へシグナルが伝わることで、精巣と卵巣が形成されるわけです。その過程でこれらの遺伝子が雄化のシグナルや雌化のシグナルとして機能すると考えられます。当初はバランスを保っていた雌雄のシグナルが、徐々にバランスを失ってゆくことで、性的に未分化だった細胞が徐々に精巣または卵巣としての機能を獲得してゆくのです。そしてこの遺伝的プログラムのもっとも上位に位置しているのが性決定遺伝子なのです。見方を変えれば、この性分化の過程は性的可塑性が失われてゆく過程と言うことも可能です。つまり、生殖腺原基がもっていた精巣へも卵巣へも分化することができる能力を失ってゆくプロセスなのです。生殖腺が他の組織と異なるのはまさにこのステップで、性決定にしたがって生殖腺原基が精巣か卵巣の一方を選択するのですが、同時に他方へ分化する能力を消失してゆきます。肝臓や心臓の原基がそのような選択をすることはありません。
さて、性決定はこの未分化な生殖腺原基に起こるイベントと考えられます。そうであれば、性決定遺伝子となるためには少なくともこの未分化生殖腺、もしくはその近傍に発現しなければなりません。しかも性的に未分化な時期の生殖腺ですから、性決定遺伝子の発現時期も限定されます。これまでに同定されたSRYとDMYはともにこの条件を満足しているのでした。もう1つの条件は、Y染色体にのみ存在し、X染色体には存在しないこと。性染色体も元は常染色体であったのだから、Y染色体にのみ存在するためには、相同遺伝子がX染色体から欠失するか、新たな遺伝子がY染色体にできるかのいずれかによります。そして、この遺伝が、すでに述べたように、生殖腺の性決定に関与し、雄化シグナルと雌化シグナルのバランスを壊すような働きをすればよいのです。といっても、そんなに簡単にそのような活性をもつ遺伝子があるのかと思われるでしょう。ところが、実際にこのような活性をもつ遺伝子が、SRY以外にも存在することが、ノックアウトマウスやトランスジェニックマウスを用いた実験で明らかにされています。ある種の遺伝子のノックアウトマウスやトランスジェニックマウスで性転換が認められているのです。つまり、雄化シグナルと雌化シグナルのバランスが、ある種の遺伝子のノックアウトやトランスジェニックで壊されたわけです。先に述べた性決定遺伝子の機能と同じです。
これらの結果は、性決定遺伝子に成り得る潜在的能力をもった遺伝子が複数存在することを示しており、これが性決定遺伝子の多様性の基盤を形成しているのだと思います。そして、これらの候補遺伝子の中から、哺乳類とメダカでは異なる遺伝子を性決定遺伝子として選んだのだと考えられます。選ばれ方は偶然であったのか、必然であったのか?必然であることに対する合理的な説明は無理でしょう。多分、偶然に選ばれたのだろうと考えるのが妥当です。選ばれ方は偶然であるにしても、性
決定遺伝子の多様性は、進化のうえで必然であったのでした。
本稿では生殖と性に関わる多様性を、マクロな視点からミクロな視点を通して議論してきました。種の多様性獲得の原動力となったのが生殖であり、そして個体間の競争が多様な生殖戦略を生み出してゆきました。生殖戦略の多様性の獲得には、性淘汰が重要な役割を演じています。一方、個体の性の決め方も多様です。環境か遺伝子か、XYかZWか。そして、性決定遺伝子の多様性。このように性に関わる事象には多様性がつきまとうのです。そしてこの多様性こそが、多様な種を確立するに至った生物進化を押し進める基盤を提供したことは間違いありません。したがって、多様性こそが性の本質を物語っていると考えられるのです。
本稿で述べた事項については、本来ならば参考文献を上げるべきですが、割愛させていただきました。


|