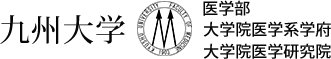2017.06.09
「ヒト iPS 細胞由来神経幹細胞の低酸素培養により、短期にアストロサイト分化を誘導」(基盤幹細胞学分野 中島 欽一教授)
| ヒト iPS 細胞由来神経幹細胞の低酸素培養により、短期にアストロサイト分化を誘導 〜神経疾患・発達障害の新たな治療法開発に期待〜 |
九州大学大学院医学研究院の中島欽一教授と、大学院医学系学府博士課程4年の安井徹郎らの研究グループは、慶應義塾大学医学部の岡野栄之教授らとの共同研究により、ヒト iPS 細胞(※1)由来神経幹細胞を低酸素培養することで、従来と比較して短期間で、脳を構成し、その機能を支持するグリア細胞の一種であるアストロサイトへの分化を誘導できる方法を明らかにし、そのメカニズムを解明しました。(図 1)
さらに、これを自閉症やてんかん、失調性歩行、特有の常同運動(手もみ動作)を特徴とする進行性の神経発達障害、レット症候群(※2)の患者由来神経幹細胞に応用することで、レット症候群患者の脳内で見られる表現型が培養系でも短期間で再現できることを世界に先駆けて発見しました。
この成果により、幅広い精神疾患・発達障害の発症原因の解明や、新たな治療薬開発につながることが期待されます。
本研究成果は、2017年6月6日(火)正午(米国東部夏時間)に、国際学術雑誌『Stem Cell Reports』のオンライン版に掲載されました。
 |
図 1 ヒト iPS 細胞由来神経幹細胞がアストロサイトへの分化能を獲得する仕組み |
| 【お問い合わせ先】 | 九州大学大学院医学研究院 教授 | ||
| 中島 欽一(なかしま きんいち) 電話:092-642-6195 FAX:092-642-6561 |
|||
| Mail:kin1(at)scb.med.kyushu-u.ac.jp ※(at)は@に置きかえてメールをご送信ください |
|||
■背 緯
中枢神経系は、共通の神経幹細胞から分化・産生された神経細胞(ニューロン)とグリア細胞(アストロサイトとオリゴデンドロサイト)を中心に構成されています。しかし、神経幹細胞は発生初期から多分化能を保持しているわけではなく、胎生中期にまずニューロンの分化能を獲得し、胎生後期になってようやくアストロサイトへの分化能を段階的に獲得します。
アストロサイトはニューロンの機能を支持する役目を担っており、ニューロンへの栄養供給以外にも、近年では軸索伸展やシナプス可塑性の制御などを介して学習・記憶にも影響を与えることが明らかにされています。また、その機能的重要性から、てんかん、ポリグルタミン病、筋萎縮性側索硬化症、アレキサンダー病、レット症候群などの多くの神経疾患の発症及び病態に関与すると考えられています。
ヒト iPS 細胞作製技術の登場により、患者由来 iPS 細胞から神経幹細胞を作製し、さらにそこから各種神経系細胞への分化を誘導することによって、培養皿の上でそれぞれの疾患に特異的な神経系細胞の機能を解析することも可能になってきました。しかしながら、ヒト iPS 細胞から作製された神経幹細胞にアストロサイトへの分化能を持たせるには、通常は胎児脳から直接得た神経幹細胞よりもはるかに長い、約200日程度の長期間培養が必要とされ、そのメカニズムも不明でした。
この異常に長い培養期間も理由の一つとなり、ヒト神経疾患特異的アストロサイトの機能解析は、ニューロンなどの解析と比較してあまり進んでいませんでした。
■内 容
研究グループは、ES 細胞もしくは iPS 細胞由来神経幹細胞は、胎児脳由来神経幹細胞と比較して幼若な状態が維持されている、あるいは発生の進行が非常に遅いのではないかと仮定して、それぞれの細胞が置かれている微小環境に着目しました。
生体内と培養系の微小環境において、大きく異なるものの1つに酸素濃度があり、生体内の酸素濃度1〜5%に対し、細胞培養時の酸素濃度は21%になります。このことから胎児脳の生体内環境を模してヒト iPS 細胞由来神経幹細胞を低酸素下で培養し、生化学、分子生物学、遺伝学を用いた実験により、アストロサイトへの分化誘導とそのエピジェネティック(※3)な制御メカニズムを明らかにする研究計画を立案しました。
ヒト iPS 細胞由来神経幹細胞に対して胎児脳内環境を模した低酸素条件下で分化誘導を行い、バイサルファイトシーケンス解析(※4)を実施した結果、転写を調節するアストロサイト特異的遺伝子のプロモーター領域(※5)が、遺伝子発現が抑制されないように脱メチル化(※6)(図 2)され、通常酸素濃度に比べて、速やかに、より多くのアストロサイトが産生される(図 3)ことが明らかになりました。
研究グループは、このエピジェネティックな性質変化のメカニズムとして、低酸素濃度での分化培養では低酸素誘導因子(HIF1α)および細胞間の情報伝達方法の一つである Notch シグナル関連因子の協調的な作用により、発生段階に沿ったヒト神経幹細胞の性質変化が誘導されることをつきとめました。(図 1)
さらに、このメカニズムを応用し、疾患モデルの一つとしてレット症候群患者 iPS 細胞由来の神経幹細胞を低酸素下に培養することで、アストロサイトを短期間で得ることに成功し、これまで知られていなかった MeCP2 が欠失したレット症候群患者アストロサイトの新たな表現型も明らかにすることに成功しました。

■効果・今後の展開
ヒトアストロサイトの機能解析を、非侵襲的に(生体を傷つけない方法で)、かつ短期間で行えることから、本研究成果は、発達障害を含めた様々な精神・神経疾患の病態解明や新規治療法の開発へと波及することが考えられます。
■【用語解説】
■【用語解説】
| (※ 1) iPS 細胞 | |
| 京都大学の山中伸弥教授らが開発した方法によって体細胞をリプログラムして作製した、様々な組織や臓器の細胞に分化する能力をもった細胞。 | |
| (※ 2)レット症候群 | |
| 自閉症やてんかん、失調性歩行、特有の常同運動(手もみ動作)を主徴とする進行性の神経発達障害。主に X 染色体に存在する MeCP2 遺伝子の変異が原因の遺伝病。 | |
| (※ 3)エピジェネティクス | |
| DNAの配列変化を伴わずに遺伝子発現を制御する細胞内プログラムを指し、DNAメチル化以外にも、DNAが巻き付 いているヒストンの修飾などによる制御を含む。 | |
| (※ 4)バイサルファイトシーケンス解析 | |
| ゲノムDNAにバイサルファイト処理を行うとメチル化シトシンは変換されず、非メチル化シトシンのみがウラシルに変換される。それを利用して、細胞内のどの遺伝子がメチル化されていたかを調べる方法。 | |
| (※ 5)遺伝子プロモーター領域 | |
| 遺伝子発現制御領域であり、プロモーター領域に転写因子が結合することで遺伝子の転写が調節されるため、この領 域のエピジェネティックな修飾は遺伝子発現の制御に非常に重要である。 | |
| (※ 6)脱メチル化 | |
| DNAメチル化は、ゲノムを構成する4つの塩基のうち、主にシトシンに起こる化学修飾の一つ。一般に、遺伝子発現制御領域においてDNAメチル化が起こると、その遺伝子の転写は抑制される。DNAメチル化パターンは個々の細胞によって異なり、それが各細胞において発現できる多くの遺伝子を規定する。脱メチル化とは、この化学修飾が外れることで、それによりその遺伝子の転写抑制が解除される。 | |